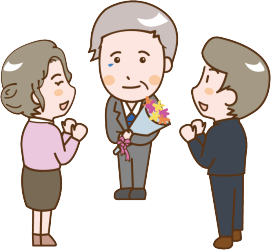(1)事案の概要
本件は、被告Y1が、原告会社Xの顧問税理士として税務申告業務等を行うとともに、コンサルティング業者である被告会社Y2の代表取締役として、Xの事業承継等についてのコンサルティング業務等に携わっていた場合に、Xら(X及びその代表取締役であった亡Aを相続した承継人)が、上記業務等に関し、被告Y1らの詐欺による報酬の不正請求があったなどと主張して、Y1らに対し、不法行為等に基づく損害金(約2億4700万円)の支払を求める事案である。
○本判決に至るまでの事実等は、次のとおりである。
① 原告ら
Xは、金型の製造等を目的とする株式会社である。A(昭和8年生)は、Xの創業者である。Aは、Xの創業以来の取締役兼代表取締役であったが、平成25年4月に取締役を辞任して代表取締役を退任し、従前から取締役であったB(Aの妻)が代表取締役に就任した。
② 被告ら
Y2は、企業の経営に関するコンサルティング業務等を目的とする会社である。Y1は、税理士兼公認会計士であり、Y2の設立以来の代表取締役である。
③ 当初の契約
Xは、平成24年12月、Y1及びY2との間で、委任業務を「記帳代行(帳簿の作成)、決算処理(決算書の作成)、税務書類作成(税務申告書の作成)、申告業務(税務申告書の提出)」等とし、顧問報酬(記帳代行を含む。)を月額52万円余、決算報酬(申告)を年額157万円余と定めて、顧問契約を締結した(以下「本件顧問契約」という。)。Xは、同日、Y2との間で、委任業務をXの自社株式移転に関するシミュレーション及び実行支援業務とし、報酬を月額52万円余と定めて、資産税コンサルティング顧問契約を締結した。なお、上記のとおり、報酬額(月額部分)の等しい2種類の顧問契約が並立したが、Y2が月々受領していた顧問報酬は、52万円余のみであった(この顧問報酬が2つの契約のどちらの月次報酬であったかについては争いがある。)。
④ 株価引き下げ業務の経緯
Xは、平成24年12月頃、発行済株式2万株(以下「本件株式」という。)の価額は、16億9634万円に高騰しており(1株当たりの価額が8万4817円であった。)、Xは、本件株式を保有していたA(当時79歳)が死亡した場合、相続人に多額の相続税が課される一方、Aが生前に本件株式を事業の後継候補者に贈与した場合、同人に多額の贈与税が課されるという状況にあった。そこで、Y1は、役員を辞任するAに退職慰労金を支給して会社資産を減らすことにより、本件株式の価額を引き下げた上、同株式を事業の後継候補者であるC(Aの長女)に贈与することを提案し、平成24年12月、Y2との間で、委嘱の範囲を「Xの株価引き下げ業務一切、生前贈与業務一切」とし、資産税コンサルティング業務報酬を1816万円余と定めて、委嘱契約を締結した。
平成25年4月、Aは、Xの代表取締役を退任して取締役を辞任し、Xは、Aに対し、退職慰労金及び特別功労金合計6億3000万円を支給した。その結果、本件株式の価額は、2億4704万円に下落した(1株当たりの価額が1万2352円になった。)。Aは、同年12月、Cに対し、本件株式2万株を贈与した。
⑤ 欠損金の繰戻還付の経緯
Aへの退職慰労金等の支給により、Xに欠損金が発生したため、Y1は、平成25年7月、欠損金の繰戻しによる法人税の還付を税務署に請求し、Xから、還付請求書の作成にかかる報酬等265万円余を受領した。同報酬と本件顧問契約の決算報酬年額との差額は、107万円余である。同年8月、Xに法人税の還付金1億1429万円余が還付され、Y2は、同年10月、欠損金の繰戻還付支援業務の成功報酬(還付金の10%相当に消費税を加算)として、Xから、報酬1200万円余を受領した。
⑥ 納税猶予支援業務の経緯
平成25年12月に本件株式の贈与を受けたCに対し、贈与税が課されることになった。これに先立ち、Y1は、Xが非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度を利用し、Cが納税猶予を申告することを提案した。ただし、Xが資産保有型会社(現預金資産等の特定資産の帳簿価額の合計額が資産の帳簿価額等の総額に対する割合が70%を超過すること)に該当し、納税猶予が取り消された場合、猶予された贈与税の納付に加え、利子税が課される不利益があった。Xは、平成25年4月の時点では上記割合が約61%であったが、同年8月、約1億1429万円余の還付を受けたため、同割合が70%を超過し、資産保有型会社に該当することになった。Xは、同年11月、Y2との間で、委嘱の範囲を「贈与税の納税猶予の実行支援業務」とし、資産税コンサルティング報酬を835万円余と定めて、委嘱契約を締結した。Xは、同年1月、納税猶予制度の利用につき経済産業大臣の認定を受け、同年3月、同猶予税額を8056万円余とする申告書を税務署に提出したが、その後、同制度の利用を中止した。そのため、Cは、同年7月、上記猶予税額と同額の贈与税を納付し、また、後日、利子税を納付した。
⑦ 株式交換による組織再編業務の経緯
Y1は、いったん下落した本件株式の価額(1株当たりの価額が1万2352円)が再び上昇した場合、Cの死亡後の相続税が高額になり納付できないおそれがあるとして、その税負担を軽減する目的で、Cが本件株式の贈与を受けるのに先立ち、株式交換制度を利用し、株式会社Gを設立した上、CがGに本件株式譲渡する代わりに、Gが新株を発行し、これをCに譲渡すること(株式交換)を提案し、これによる相続税軽減額が2億2730万円であると説明した。Xは、平成25年9月、Y2との間で、委嘱の範囲を「株式交換による組織再編業務」とし、資産税コンサルティング報酬を1374万円余と定めて、委嘱契約を締結した。平成26年1月、Gが設立された。Gは、同年6月、Xとの間で、株式交換契約を締結し、同年8月、同契約に基づき株式交換が行われた。
⑧ 上記以外の争点となったX、A及びCに関するY1及びY2の業務に、遺言書作成支援業務、一般社団法人活用支援業務、地方税の繰戻還付請求、ふるさと納税事務代行に関するものがある。
(2)判決要旨(一部認容・一部棄却)
① 株価引き下げ業務の目的や経緯は合理的なものであった。実際に、Xでは、役員退職慰労金規定の制定、Aの取締役辞任(代表取締役退任)と退職慰労金等の受領、Cに対するXの株式の贈与が実現し、同株式の価額は前決算期から7分の1以下に下落して相当の贈与税軽減効果が発生した。報酬は高額であるが(合計1816万円余)、税効果の4%相当という算定根拠は、社会的相当性を逸脱するほどではない。したがって、株価引き下げ業務につき、Y1が重複請求を企て、その報酬を詐取したと認めることはできない。
② 確定申告書と同時に還付請求書を提出するため、税理士は、通常の顧問報酬とは別個に還付請求支援の報酬を請求しないのが一般的であり、別個に請求するとしても、作業量に照らして不相応に高額な報酬を請求することは望めない。欠損金の還付支援業務の成功報酬(還付金の10%相当に消費税を加算)は、独自の業務実態が認められず、還付請求書の作成報酬との重複請求である。その額は不相応に高額であり、報酬目当てという不正な動機もうかがわれ、報酬請求は不当性、不合理性が著しく、Y1が報酬を詐取したと認められる。したがって、報酬相当額1200万円余につき、Y1は不法行為責任に基づき、Y2は、役員等の第三者に対する責任及び代表者の行為についての責任に基づき、Xに対し、損害賠償義務を負う。
③ 平成25年4月期末において、Xの総資産に対し現預金が占める割合は約61%であったが、平成25年8月に約1億1429万円の法人税の繰戻還付を受けて現預金が増加したため、その頃以降、同割合が約76%に達し、Xは資産保有型会社に該当し、納税猶予の取消事由が発生していた。ところが、Y1は、その後に行った納税猶予の申告において、Xを資産保有型会社に該当するものと扱わず、上記割合を約61%のままにしていたのであり、納税猶予の取消事由が発生していたことを見落としていたと認めることができる。しかも、Xに対し欠損金の繰戻しによる法人税の還付を受けることを提案して実行したのはY1自身であったことを考慮すると、この見落としに同被告の重大な過失があったというべきである。したがって、報酬相当額合計845万円余につき、Y1は不法行為責任に基づき、Y2は、役員等の第三者に対する責任及び代表者の行為についての責任に基づき、Xに対し、損害賠償義務を負う。
④ 株式交換による組織再編業務の主要な目的は、Cの死亡後の相続税の軽減を図ることであったが、その提案時(平成25年8月)には、Cはまだ54歳であり、数年内に相続税の軽減を図る必要に迫られているわけではなかった。Cの死亡後の相続税額に株価再上昇の影響が及ばないようにするには、相続時精算課税制度の採用等、他の方策の選択もあり得たのであり、株式交換による組織再編業務は、業務実態がなかったわけではないものの、これを実行することには疑問があり得た。株式交換による組織再編業務は、平成25年ないし翌26年頃に提案して実行する必要性がなく、税効果も不確かで、意味合いの乏しいものであったというほかない。Y2は、無意味な業務をあえて実行したことにより不相応に高額の報酬を取得したのであり、暴利行為があったと認めることができる。したがって、株式交換による組織再編業務にかかる委嘱契約は、暴利行為により無効であり、報酬相当額1374万円余の損失につき、Y2は、Xに対し、不当利得返還義務を負う。
⑤ Xに対して、Y1らは、合計約1億900万円の損害賠償債務ないし不当利得返還債務を負う。