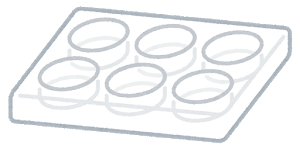役員退職金の額は、原則として、役員等がその法人から現実に退職して支給されたものである限り法人税法上、損金算入が認められ、また、所得税法上も退職所得としての課税の恩恵が受けられます。
しかしながら、例外として、現実には退職したという事実は認められないが、実質的には退職したものと同様の事態に至った場合に支給されるものについても、その支給時に法人税法上の退職給与として損金算入が認められ、所得税法上も退職所得とするように弾力的に取り扱われることがあります。
例えば、法人が役員の分掌変更等に際し、その役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等により、その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことにしています(法基通9-2-32、同旨所基通30-2(3))。
① 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
② 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
③ 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
通達改正1
上記の通達は、平成19年3月に、上記③の下線されている部分が改正されたのですが、それは、形式的に報酬(給与)の額を50%以上引き下げればその際にその役員に支給した臨時的な給与はすべて退職給与として損金算入することが可能であるとする、誤った理解に基づく事案が目立ったことによります(京都地裁平成18年2月10日判決・税資256号順号10309、大阪高裁平成18年10月25日判決・税資256号順号10553等)。
京都地裁判決では、同族会社の代表取締役であったQが平取締役へ異動し、報酬を50%超減少(月額95万円から45万円)させて退職慰労金4,000万円を支払っていた事案について、「Qが、(省略)、原告の重要な業務を担当していることを考慮すると、Qの報酬が形式的には半額以下となったことをもって、Qが原告を退職したのと同様な事情があると認めることはできない。本件通達も、形式的に本件通達①から③までのいずれかに当たる事実がありさえすれば、当然に退職給与と認めるべきという趣旨と解することはできない。」として、役員退職給与を否認し損金算入を否認する更正処分を認めています。
分掌変更に伴い支給された役員退職給与については、その支給額が「不相当に高額な部分の金額」(法法34 ②)があるか否かよりも、「実質的に退職したと同様の事情」にあるか否かで、課税庁側と争われることが多いです(そもそも、実質的に退職したと同様の事情がないのであれば、全額損金不算入となるので、不相当に高額な部分の金額があるかが否かについて争う理由がない)。そして、裁判所や審判所が「実質的に退職したと同様の事情」にあるか否かを判断する場合には、分掌変更後の事実認定がポイントとなります。
中小企業における分掌変更に伴う退職給与の支給については、多額の保険金が入ったり、自社株式の評価額の引下げを意図したり、非上場株式の納税猶予制度の適用といった際に行われる場合が多いです。しかしながら、判断を誤ると、法人税、所得税の両方にわたり当初想定していた納税額とは全く違ったものになってしまうという課税リスクがあるので、実行前には慎重に検討をする必要があります。
通達改正2
平成19年3月のもう1つの改正は、注書きで「本文の『退職給与として支給した給与』には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。」と追加されたことです。
定年の延長等に伴い退職給与規程を制定又は改正し、使用人に対して退職給与を打切支給した場合等については、従来から未払金等に計上した場合は含まれないとされていました(法基通9-2-35、9-2-36 (注))。
しかしながら、そのことは本通達については明記されていないことから、未払金等に計上した場合でも認められるのではないかという考え方に基づく事案(東京地裁平成17年12月6日判決・税資255号-順号10219、東京高裁平成18年6月13日判決・税資256号順号10425など)が目立ったことにより改正となりました。その中で、東京高裁平成18年6月13日判決(税資256号順号10425)は、次のとおり判示しています。
「本件通達9-2-23(編注:現行の9-2-32)が、本来退職しない役員に対する退職給与であって、法人税法上損金算入されないのに、分掌変更等の場合に限り、税務上も退職給与として損金算入することを認めたものであり、役員が引き続き在職する場合の役員退職給与について、一種の特例的な取扱いを明らかにしたものと解されることに照らし、上記通達が実際に支払がされた場合にのみ適用されるものとして、法人税法上の債務確定主義の例外を定めたものと解したとしても、特に不合理であるとはいえない。以上のとおり、本件通達9-2-23は、現実に支払がされた退職給与について適用されるものと解すべきであ(る。)」
ただし、役員退職給与という性格上、その法人の資金繰り等の理由による一時的な未払金等への計上までも排除することは適当ではないことから、「原則として、」という文言が付されています。
なお、課税庁職員が執筆している「法人税基本通達逐条解説 八訂版」(小原一博編著/税務研究会出版局/平成28年7月1日発行)における法人税基本通達9-2-32の解説では、七訂版と比して次の記述が追加されています。
「ところで、このように、原則としては未払金等への計上を認めないとしていることとの関係上、退職金を分割して支払いその都度、損金算入するといったことも認められないのではないかと見る向きがある。この点、役員の分掌変更等が実質的に退職したと同様の事情にあることが前提であることは言うまでもないが、分割支払いに至った事情に一定の合理性があり、かつ、分掌変更段階において退職金の総額や支払いの時期(特に終期)が明確に定められている場合には、恣意的に退職金の額の分割計上を行ったと見ることは適当ではないことから、支払いの都度損金算入することが認められると考えられる。」
これは、分掌変更による役員退職給与を分割払いのつど損金算入することの是非が争われた事例(東京地裁平成27年2月26日判決・平成24年(行ウ)第592号)で、課税庁の更正処分等の全てが違法とされ取り消しとなった結果を受けて追加されたと思われます。
役員の分掌変更に伴って同族会社が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、退職給与に該当しないとされた事例-平成29年7月14日裁決(裁事108集)(棄却)
(1)事案の概要
本件は、スクラップ加工等を行う同族会社である審査請求人X(以下「X」という。)が、役員A(以下「A」という。)の分掌変更に伴いAに対し退職慰労金として支給した金員(以下「本件金員」という。)について、原処分庁が、Aは分掌変更により実質的に退職したと同様の事情にあるとは認められないから、本件金員は退職給与ではなく損金の額に算入されない役員給与であるとして法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をするとともに、本件金員は給与所得に該当するとして源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしたことに対し、Xが、本件金員は退職給与ないし退職所得であるとして、処分の全部取消しを求めた事案である。本件は、同族会社がその役員の分掌を変更し、かつ、その給与を50%以上減額した際に退職慰労金として金員を支払った場合に、その金員が法人税法上の「退職給与」として所得金額の計算上損金の額に算入し得るか、また、その金員が所得税法上の「退職所得」として課税軽減の適用が認められるか、が争われたものである。
○本件における基礎事実等は、次のとおりである。
①Aは、Xの設立時取締役であり、昭和41年7月、Xの代表取締役社長に就任した。また、Aの長女であるBは、平成18年1月、Xの代表取締役に就任した。
②Xの発行済株式の総数は10,000株であるところ、平成11年頃から、Aが500株、Bが4,000株、Bの夫でXの取締役であるFが1,750株、G社が3,750株を保有していた。なお、Aは、G社の株式を保有していない。
③Aは、平成17年8月、平成21年7月にそれぞれ深刻な病気となり、入院したことがあり、平成22年7月に再度病気となった。その後、Aは治療のために通院を続けた。
④平成23年5月、Aは、Xの代表取締役社長を辞任し、代表権のない取締役会長となった(以下、このAの役職の変更を「本件分掌変更」という。)。本件分掌変更後のXの代表取締役はBのみであり、Xの取締役はA、B及びFであった。
⑤平成23年5月20日付の臨時株主総会において、Xは、本件分掌変更に際しAに対して退職慰労金を支給することを決議し、同月26日付でAに対し当該退職慰労金(所得税等控除後の残額)を支払った。Aの平成23年7月分の給与額は、改定前の平成23年6月分の給与額に比べて約55%減少した。ただし、当分の間、Aは、本件分掌変更後も、後任の代表取締役であるBの役員給与額の2倍の給与額を受け取っていた。
⑥Xは、平成22年6月1日から平成23年5月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)において、本件金員を役員退職金勘定に計上し、本件事業年度の法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入して、法定申告期限までに確定申告した。また、平成23年6月10日、Xは本件金員が退職所得に該当するとして、本件金員に対する源泉所得税を納付した。
⑦平成27年7月、Aは、Xの代表取締役に再度就任した。
⑧平成28年5月31日、所轄税務署長は、本件事業年度の法人税について、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。同日、平成23年5月分の源泉所得税について、納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をした。
○本件分掌変更後の事実は、次のとおりである。
① Aの出勤状況
Aは、本件分掌変更前は、ほぼ毎日、午前6時から6時半頃Xに出社し、午後4時から5時頃退社していたところ、本件分掌変更後は、ほぼ毎日、午前7時から8時頃Xに出社し、午前中に退社していた。また、Aは、発病直後を除き、本件分掌変更前後を通じ、自ら自動車を運転して通勤していた。
② 本件分掌変更後の取引先との折衝等
Aは、本件分掌変更の後、流れ屑の取引価格及び配合方針の決定に係る権限をF等に徐々に移譲するようになった。ただし、権限移譲の過程においても、Aは、単発的に発生する流れ屑の取引価格についてF等から相談を受けてアドバイスをしたり、流れ屑の輸入取引に係る取引条件について取引先から直接連絡を受けることがあった。また、Aは、本件分掌変更後の平成24年2月頃まで、少なくとも22回以上、Xの取引先の幹部に対して飲食等の接待をした。
③ 本件分掌変更後の金融機関との折衝等
Aは、本件分掌変更の後、融資交渉等の金融機関との折衝に係る権限を徐々にBに移譲するようになり、Bが金融機関からの借入れの申込みを行うようになった。また、本件分掌変更に伴い、Aは金融機関から同意を得て、Xの連帯保証人の地位から脱退した。なお、権限移譲の過程で、Aは、Bと金融機関との借入れに係る利率等の条件交渉の場に立ち会い、自らの意見を述べることもあった。
④ 本件分掌変更後の人事関係の決定等
Aは、本件分掌変更前、従業員の採用決定に関与するとともに、従業員の給料や賞与の査定を行っていたが、本件分掌変更に伴い、それらに係る権限をB及びFに移譲した。
Aは、平成23年7月18日、Xの取締役会に出席し、B及びFと共に、役員給与の変更について決定した(平成24年7月30日の取締役会においても同じ)。また、Aは、平成25年5月、横領等の不正行為を働いた事業所長の解雇を、B及びFと共に決定した。
⑤ 本件分掌変更後の事業所に係る支出等
Aは、本件分掌変更前と同様、取締役であるA、B及びFのみを構成員として年5、6回不定期に開催される経営会議に出席し、数千万円から1億円超にも及ぶ事業用資産の購入をB及びFと共に決定した。また、Xは、本件分掌変更前後を通じ、Xの事業所の操業継続に支障を及ぼす周辺の住民との間のトラブル(騒音、振動等に関するもの)を抱えており、Aは、そのトラブルの解決のために住民などに金員を渡すこととし、本件分掌変更前後を通じ、必要に応じて、Bに出金を指示して、住民などに金員(本件事業年度やその翌事業年度においては申告所得額の約1割に相当する額)を支払っていたが、その詳細については、B及びFに知らせていなかった。
(2)裁決要旨
①法人税法上の退職給与該当性について
本件分掌変更に伴い、Aの地位や職務につき相当程度の変動が生じたことは認められるものの、Aは、本件分掌変更後も、Xの経営ないし業務において主要な地位を占め、Xの取締役として重要な決定事項に関与していたことが認められるから、Aは、本件分掌変更により、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、本件金員は法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないものと認められる。
②所得税法上の退職所得該当性について
Aは、Xを退職しておらず、また、本件分掌変更によって、役員としての地位又は職務の内容が激変したとは認められないから、本件分掌変更に伴い支給された本件金員は退職所得に該当しない。そして、本件金員は、本件分掌変更後も引き続きXの取締役の地位を有し、重要な決定事項に関与するなどしていたAに対して、取締役としての稼働に対する対価として臨時的に支給されたものであると認められるから、その収入に係る所得は、所得税法第28条第1項に規定する給与所得(賞与)として認めるのが相当である。