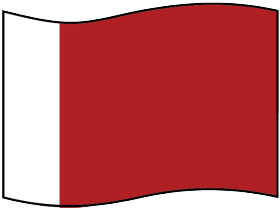概要
法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち損金の額に算入されないものが、法人税法38条等に列挙されています。そして、法人税法38条等に列挙されていない残りの租税公課が損金に算入されるものとなります。
ですから、まず、損金の額に算入されない租税公課を理解するのが早いです。
損金の額に算入されない租税公課
損金の額に算入されない主な租税公課は、次のものです(法法38、40、55③)。なお、法人が決算で損金経理をした租税公課のなかに損金不算入のものがあれば、その金額を租税公課の納付状況に関する明細書(申告書別表五(二))に記入し、申告書別表四で所得金額に加算します。
(1)法人税、地方法人税及び住民税
法人税、地方法人税及び住民税(都道府県民税、市町村民税)を損金の額に算入しないのは、本来その所得の中から支払われることを前提としているものですから、これを損金の額に算入すると、法人の所得そのものが循環的に増減し、各期ごとに所得のばらつきが生ずることにもなるので、これを排除するため損金としないこととされています(法法38①、38②二)。
なお、ここで法人税、地方法人税及び住民税の額という場合には、これらの本税に係る加算税等の附帯税は含まれません(下記(2)参照)。また、事業税・特別法人事業税は、法人税法38条で列挙されていませんから、損金の額に算入されます。
(2)国税の附帯税(利子税を除く)、印紙税の過怠税、地方税の延滞金・加算金
これらは法律どおり申告や納税をしなかったことに対して課される一種の行政上の制裁に関するものです。これらを損金に算入すれば、これに対応して減少する税額に相当する部分の制裁効果を減殺させる結果となるため、損金としないこととされています(法法55③)。
これらに該当するものとしては、国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税の過怠税、地方税法の規定による延滞金(納期限延長の場合の延滞金を除く。)、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金がある。
なお、法人税の申告期限の延長にともなって納付する利子税については、制裁の意味合いがないので損金に算入されますので注意をしてください(法法38①三、通法60④、64③、69)。地方税における納期限の延長の場合の延滞金も同様です。
(3)罰金、科料、過料、交通反則金等
これらは、社会秩序維持のために課されるものであり、(2)と同様の理由により損金としないこととされています(法55④)。また、外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものは、国内の罰金及び科料と同様に損金の額に算入しないこととされています(法法55④一)。
なお、法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とします(法基通9-5-8)。
(4)法人税額から控除する所得税額
利子、配当等について源泉徴収された所得税を法人税額から控除する場合は、その控除する所得税額は法人税額の前払金に相当するので損金としないこととされています(法法40)。
(5)外国税額控除の対象とした外国法人税額等
- 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入(法法39の2)
- 法人税額から控除する外国税額の損金不算入(法法41)
- 分配時調整外国税相当額の損金不算入(法法41の2)
損金の額に算入される租税公課
損金の額に算入される主な租税公課は、以下の通りです。
(国税)消費税(税込経理方式)、印紙税、酒税・その他の個別間接税、利子税、法人税から控除しない所得税
(地方税)事業税・特別法人事業税、固定資産税・都市計画税、納期限延長の場合の延滞金
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです(法基通9-5-1、9-5-2)。
(1) 申告納税方式による租税
事業税・特別法人事業税、消費税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した日を含む事業年度(つまり、翌事業年度)に損金算入となります。
また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
したがって、事業税については、確定申告分の税額は翌期の損金に算入されるということです。同様に、中間納付した事業税が確定申告により一部還付になる場合も、翌事業年度の益金として計上する処理は認められるものと考えます。
なお、その事業年度の直前事業年度分の事業税・特別法人事業税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます(法基通9-5-2)。
この取扱いの趣旨について、「十訂版法人税基本通達逐条解説(税務研究会出版局発行)」1052頁では、以下のように解説されています。
| 事業税については、原則として法人税法上の所得金額をその課税標準とするものであるため(地方税法72の12)、法人税の更正、決定等に連動してその課税が修正されるという事情がある。そこで、法人税についていわゆる2期以上の連年同時更正を行う場合には、その担税力等を考慮して、本通達において、たとえ翌事業年度末までに事業税の全部又は一部につき申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その納付すべき税額を見積り、これを翌事業年度の損金に算入することができるという事業税の損金算入時期の特例が定められている。 |
この場合の経理処理は、確定した決算において損金の額に算入することは要件とされておらず、申告調整により損金処理することも認められています。
ただし、直前年度分の事業税及び特別法人事業税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則として行われません(法基通9-5-2(注)2) 。
つまり、前期の事業年度において、他にも更正項目があれば、前期の事業税認定損が認容されますが、事業税の認容しかない場合は、それについての減額更正は原則として行われないということです。
あくまでも、原則ですので、税務署長の裁量により事業税及び特別法人事業税の損金算入だけを内容とする減額更正を行う余地があるものとされています。
また、消費税を税込経理方式をしているときは、決算期末に申告期限が未到来の税額を損金経理で未払計上することが認められています(消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて⓻⑧)。
| 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて (消費税等の損金算入の時期) 7 法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。 (消費税等の益金算入の時期) 8 法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が還付を受ける消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金の額に算入し、更正に係る税額については当該更正があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該法人が当該還付を受ける消費税等の額を収益の額として未収入金に計上したときの当該金額については、当該収益に計上した事業年度の益金の額に算入する。 |
事業税等は申告納税方式による租税であり、損金の額に算入される事業年度は、事業税等申告書を提出した日の属する事業年度とされた令和3年5月21日裁決(東裁(法)令2第84号)要旨
申告納税方式による租税の損金算入の時期は、法人税基本通達9-5-1の(1)において、債務確定基準の趣旨から、申告納税方式による租税については納税者のする申告により納付すべき税額が確定するものであり、原則としてその租税債務が具体的に確定した事業年度において損金の額に算入すべきものと考えられることからすると、本件通達の定めは当審判所においても相当であると認められる。
本件についてみると、事業税等は申告納税方式による租税であり、請求人は、令和元年5月24日に本件事業税等申告書を提出したのであるから、事業税等申告書の提出により、請求人の納付すべき税額として事業税等の額に係る債務が確定したものと認められる。そうすると、本件事業税等の額が損金の額に算入される事業年度は、事業税等申告書を提出した令和元年5月24日の属する事業年度(本件事業年度の翌事業年度)となる。
(2) 賦課課税方式による租税
不動産取得税、自動車税、固定資産税・都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった日を含む事業年度に損金算入となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
(3) 利子税・延滞金
国税の利子税や、地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。