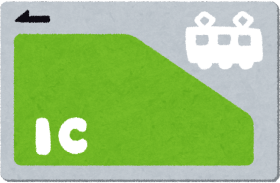概要
有限責任事業組合(日本版LLP)の組合員は、全員が業務執行を行うことが必要です。すなわち、組合員は何らかの形で、業務執行を行うことが必要であり、業務執行の全部を他の組合員に委任することはできません。つまり、出資のみの組合員は排除されています。
LLPでは、組合契約に基づき、組合員全員がそれぞれの個性や能力を活かしつつ、共通の目的に向かって主体的に組合事業に参画するという制度のニーズに基づいて導入した制度です。
そのため、組合員全員の業務執行への参加が義務付けられています。 なお、こうした組合員への業務執行への義務付けは、損失の取込だけを狙った租税回避目的の悪用を防ぐ効果もあります。
業務執行とは
業務執行の内容としては、例えば、対外的な契約締結などのLLPの営業に関する行為や、その契約締結のための交渉、あるいは、具体的な研究開発計画の策定・設計、帳簿の記入、商品の管理、使用人の指揮・監督等、組合の事業の運営上重要な部分が含まれます。
有限責任事業組合の事業から生じる収益の全てが一人の組合員に帰属するとされた事例-東京地裁令和6年2月16日判決(令和元年(行ウ)388号)(棄却)(確定)
(1)事案の概要
原告Xは、自らが設立した有限責任事業組合(以下「本件事業組合」という。)の組合員として、その化粧品及びサプリメントの販売事業(以下「本件事業」という。)に従事していたところ、所轄税務署長から、本件事業から生じた収益は全てX一人に帰属するものとして、平成25年分ないし平成28年分の所得税等に係る更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)を受けた。これに対し、Xが、本件更正処分等は違法であるとして、その取消しを求めた。なお、本件事業は多額の利益を得ていた。
(2)本件の主な争点
本件更正処分等において、本件事業に係る収益等が全てXに帰属する又は全てXが行ったものとして、その所得金額の計算を行うことが適法であるか否かである。
(3)判決要旨(棄却)(確定)
① 有限責任事業組合の組合員の当該組合事業に係る損益の額は、原則として、当該組合の損益の額のうち分配割合に応じて分配を受け又は負担すべき損益の額であるが、組合員が当該組合事業の業務執行に関与しないなど、組合員としての地位が単なる名義人にすぎず、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、当該収益は、当該収益を享受する者に帰属したものとして、所得税法の規定を適用するのが相当である(所得税法12条参照)。
② 有限責任事業組合の組合員は、全員が何らかの形で業務執行を行うことが必要とされているところ、その趣旨は、そもそも有限責任事業組合が、組合員全員がそれぞれの個性や能力を生かしつつ、共通の目的のために主体的に組合事業に参画することを可能とするために導入されたものであることに加え、損失の取込みだけを狙った租税回避目的の悪用を防ぐことにあると解される。そうすると、有限責任事業組合の組合員が行う必要のある「業務執行」とは、対外的な契約締結に関する行為やそのための交渉、具体的な研究開発計画の策定・設計、帳簿の記入、商品の管理、使用人の指揮・監督等、当該組合事業の運営上重要なものを指すものと解すべきであり、組合員が上記のような組合事業の運営上重要な業務を行っていないときは、当該組合員の組合員としての地位は、単なる名義人にすぎないものと認めるのが相当である。
③ 本件事業組合契約書には、X及びその親Hら3人が出資する旨記載されているものの、実際には、本件事業組合に対する出資は、その全額がXによるものであり、Xの出資割合が100%である上、本件事業に係る契約の締結やそのための交渉、商品の価格の決定や受発注その他商品管理、本件事業組合名義口座や現金の管理等、本件事業の運営上重要な業務については、専らXの判断や指示により行われており、また、本件事業組合名義口座からは、X個人名義の高級外車の代金やその駐車場の賃料、Xの自宅の賃料が支払われるなど、Xは、本件事業に係る収益を享受していると認められる。
④ Hらは、いずれも本件事業組合契約上、本件事業組合の組合員とされているものの、本件事業につき、有限責任事業組合の組合員が行う必要のある「業務執行」を行っていたとはいえず、その組合員としての地位は、いずれも単なる名義人にすぎず、本件事業の収益を享受していないのに対し、専らXが本件事業に係る「業務執行」を行い、その収益を享受しているといえるから、本件事業の収益については、所得税法12条に照らし、全てXに帰属し又は全てXが行ったものとするのが相当である。