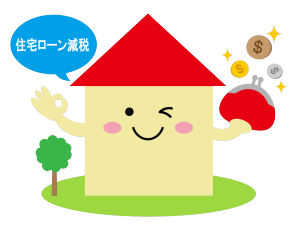所得税
不動産を貸し付けたことにより、賃貸人が敷金、保証金等の名目により収受する金銭等(以下「敷金等」という。)は、本来は賃借人の債務を担保するためのものであり、それ自体は賃貸人の収入ではありません。
ただし、授受される敷金等のなかには、契約当初から、あるいは一定期間が経過すると、その一部ないし全部が賃貸人に帰属する(返還を要しなくなる)ことが契約書などで取り決められている場合があります。
このようなものは、実質的には権利金と変わりがなく、不動産所得の収入金額となります。
よって、敷金等の額のうち、次に掲げる金額は、それぞれ次に掲げる日の属する年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入することになっています(所基通36-7)。
(1) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととなっている部分の金額がある場合におけるその返還を要しないこととなっている部分の金額
貸付けに係る契約に伴いその貸付資産の引渡しを要するものについてはその引渡しのあった日(又は契約の効力発生の日)、引渡しを要しないものについてはその貸付けに係る契約の効力発生の日
(2) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなる部分の金額
その貸付けに係る契約に定められたところによりその返還を要しないこととなった日
(3) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額
その不動産等の貸付けが終了した日
法人税
賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額(賃貸借の開始当初から返還が不要なものを除く。)であっても、期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入します(法基通2-1-41)。
賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額で、賃貸借の開始当初から返還が不要な場合には、原則としてその取引の開始の日の属する事業年度の益金の額に算入します(法基通2-1-40の2)。
建物の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は賃貸借契約を締結した時であるとされた事例(昭和47年4月24日裁決・裁事4集10頁)要旨
建物の賃貸借契約において、解約時に賃貸期間の経過に関係なく収受した敷金の一定割合を返還しないことを定めている場合には、その敷金のうち返還を要しない部分の金額の益金算入の時期は、賃貸借契約が締結された時と解すべきである。
返還を要しないことが契約当初から確定している敷金は、貸室を引渡し、当該敷金を収受した事業年度の収益に計上するのが相当であるとされた事例(昭和49年11月2日裁決・裁事10集25頁)要旨
請求人が貸室を賃貸するに当たり、賃借人から受領した敷金のうち、補修費相当額は、契約当初から返還を要しないものであり、その名称にかかわらず請求人が自ら処分することのできる金員と認められるのであるから、貸室を引き渡し、敷金を収受した事業年度の収益と認めるのが相当である。
消費税
賃貸借契約等の終了や一定期間経過後に返還する敷金等については、その実質は預り金であり、資産の譲渡等の対価ではないので、消費税は不課税とされています。
ただし、解約等の際に賃貸物件を原状に回復する義務がある賃貸借契約の場合において、賃貸人が賃借人に代わって行う原状回復工事は、賃貸人の賃借人に対する役務の提供として、消費税の課税対象となります(消法2①八、消基達5-5-1)。
したがって、原状回復工事を行いその費用相当額を賃借人からの敷金等から差し引くことは、賃貸人の提供した役務の対価を受領したことになりますから、その費用相当額は、賃貸人の課税売上となります。
なお、居住用アパートの賃貸人が、賃借人が退去する際に敷金等から差し引いた原状回復費であっても、課税売上となります。