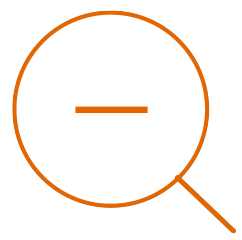概要
公益法人制度改革により、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、従来の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、一般社団法人・財団法人を登記のみで簡便に設立できる制度が平成20年12月1日から施行されました。
一方で、一般社団・財団法人のうち、法定の基準(認定法5)を充足するものとして認定を受けた公益法人については、設立後も、認定法所定の監督を行うことにより(認定法1章2節、29②一、二等)、高い公益性を保持させることとされ、公益社団法人・財団法人(法法2六)となります。
また、一般社団法人・財団法人(公益社団法人・財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものを一般社団法人・財団法人(非営利型法人)といいます(法法2九の二、法令3)。
| イ 非営利性が徹底された法人 その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして一定のもの ロ 共益的活動を目的とする法人 その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして一定のもの |
なお、一般社団法人・財団法人のうち、非営利型法人でないものは、法人税法上、普通法人として取り扱われます。
3つの分類
上記のことにより、社団法人・財団法人は、法人税法上の取扱いでは、大きく分けて以下の3つに分類されます。
①公益社団法人・財団法人、②一般社団法人・財団法人(非営利型法人)、③一般社団法人・財団法人(普通法人)
法人税の課税所得の範囲は、次のように取り扱われています。一般社団法人・財団法人(普通法人)は全ての所得に対して課税されますが、公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人(非営利型法人)は、収益事業から生じた所得にのみ課税されます(法法4①ただし書、5、7)。
収益事業とは、法人税法施行令5条に列挙されている物品販売業等の34の事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)で継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法法2十三)。
| 物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業 |
次に、利子等に係る源泉所得税の非課税については、次のように取り扱われています。公益社団法人・財団法人については、所得税法別表第一(公共法人等の表)に掲げられ、これらの法人が支払を受ける一定の利子等に係る源泉所得税は非課税とされます(所法 11①)。
一方、一般社団法人・財団法人については、法人税法上、非営利型法人及び非営利型法人以外の法人(普通法人)のいずれに該当する場合であっても、この取扱いの適用はありません。
| 法人の種類(法人税法による分類) | 課税所得の範囲 | 利子等に係る源泉徴収 |
|---|---|---|
| 公益社団法人・財団法人 | 収益事業 | なし |
| 一般社団法人・財団法人(非営利型法人) | 収益事業 | あり |
| 一般社団法人・財団法人(普通法人) | 全所得 | あり |
法人税の確定申告
(1)公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人(非営利型法人)で収益事業を営んでいない場合
法人税の確定申告書の提出義務はありません。ただし、事業年度の収入金額の合計額が8,000万円超の場合には、事業年度終了の日の翌日から4か月以内に、その事業年度の損益計算書又は収支計算書を、所轄税務署長に提出しなければなりません(措法68の6、措令39の37、措規22の22)。
(2)公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人(非営利型法人)で収益事業を営んでいる場合
収益事業に係る所得は課税対象となるので、法人税の確定申告書を提出する必要があります。確定申告書を提出する際には、貸借対照表、損益計算書等の書類を添付することになりますが、これらの書類には収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれます(法法74③、法基通15-2-14)。
(3)一般社団法人・財団法人(普通法人)
普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となりますから、法人税の確定申告書を提出する必要があります(法法74)。株式会社や合同会社と変わらない税務上の取扱いをされます。
一般社団法人・財団法人(非営利型法人)の課税上の問題点
一般社団法人・財団法人(非営利型法人)と、公益社団法人・財団法人については、以下の異同があることになります。
法人税法上は、どちらも公益法人等に区分(法人税法別表第二)され、収益事業にしか法人税が課されません。一方、所得税法上(所法11 ①)は、利子・配当等に対して源泉徴収されない法人(公共法人等「所得税法別表第一」)に一般社団法人・財団法人(非営利型法人)は含まれていません。
そして、一般社団法人・財団法人(非営利型法人)で収益事業以外の事業から生ずるものに対する所得税額は、所得税額控除の対象となりません(法法68)。
なお、一般社団法人・財団法人(非営利型法人)が収益事業を行っている場合において、収益事業に属する預貯金等から生じた利子等に対して課された所得税の額があるときには、その所得税の額は、法人税の申告に際して、法人税の額から控除・還付することはできます(法法68)。
しかしながら、一般的に、一般社団法人・財団法人(非営利型法人)は利子・配当等について収益事業としていないため、源泉徴収されたが控除・還付されないという現状です。
例え、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、その預金、有価証券等のうち収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産(公益事業に属する資産)として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為(資産運用益)は、収益事業に付随して行われる行為(つまり、収益事業)に含めないことができます(法基通15-1-7)。
仮に、収益事業とした場合は、法人税の課税対象となるため、法人側に利子・配当等を収益事業とするメリットはありません。
財団法人の場合、所有する基本財産又は運用財産を運用して得られる運用益を財源として運営を行っており、利子及び配当等は多額に生じ、結果、それに対する源泉所得税も多額となる場合があります。
東京地裁令和4年1月14日判決(令和2年(行ウ)375号)において、非営利型の一般財団法人の源泉徴収された所得税の額は8340万円余でしたが、その金額が還付となるのかならないのかは、財団法人にとっては大きな問題でしょう。
なお、外国税額控除にも注意が必要です(法法69⑬)。
割引債の償還時における源泉徴収
普通法人と同様に、一般社団法人・財団法人において利付債の利子を受取った時には源泉徴収されます。
一方、普通法人は割引債の償還時に償還差益に対する源泉徴収は行われませんが、一般社団法人・財団法人の場合には源泉徴収されます。
この理由は、一般社団法人・財団法人(非営利型法人)が税操作をしないようにするためです。
例えば、割引債の償還時に償還差益に対する源泉徴収が行われなければ、一般社団法人・財団法人(非営利型法人)は、利付債を購入せずに割引債の購入だけをするでしょう。
上記で説明したように、利付債を購入し、利子を受取った時には源泉徴収されますが、収益事業としていない場合は、源泉徴収されたが控除・還付されないという現状です。
利子と償還差益という同じような経済的利益を受けているのに、税負担が違えば、法人としては、当然、税負担が低い(ない)商品を購入します。
よって、税操作を封じるために、普通法人は割引債の償還時に償還差益に対する源泉徴収は行われませんが、一般社団法人・財団法人の場合には源泉徴収されるというわけです。
なお、一般社団法人・財団法人(普通法人)の場合は、株式会社や合同会社等の普通法人同様であり、源泉徴収を行わなくても、償還差益は法人税の課税対象となるので、本来的には問題ないはずです。
しかしながら、公益社団法人・財団法人と違い、一般社団法人・財団法人(非営利型法人)と一般社団法人・財団法人(普通法人)の外形的な違いがなく、源泉徴収義務者からすると判別が難しいため、一般社団法人・財団法人(普通法人)の場合も源泉徴収されるというわけです。
関連記事
非営利型の一般財団法人で収益事業から生じた所得以外の所得で法人税が課されないものである場合、利子及び配当等について徴収された所得税の額は法人税の額から控除・還付することはできないとされた事例-東京地裁令和4年1月14日判決(令和2年(行ウ)375号)(棄却)(控訴)
(1)事案の概要
本件は、非営利型法人(法人税法2条9号の2)に該当する一般財団法人である原告Xが、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税について、収益事業以外の事業に属する資産から生じた利子及び配当等(以下「本件利子及び配当等」という。)について源泉徴収された所得税の額に相当する8340万円余を含む8395万円余の還付(法人税の額から控除しきれなかった所得税の額の還付)を求める更正の請求をしたところ、所轄税務署長から、更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けたことから、非営利型法人であるXの利子及び配当等については非課税とされるべきであるなどとして、Xがその取消しを求めた事案である。
(2)本件の主な争点
更正の請求に理由がないとした本件通知処分が適法であるか否かである。具体的には、①本件利子及び配当等が非課税となるか否か、②本件利子及び配当等に係る所得税額の還付等が認められるか否かである。
(3)判決要旨(却下・棄却)(控訴)
① Xは、非営利型法人に該当する一般財団法人であって、公益法人ではないから、Xが所得税法別表第1に掲げる公共法人等として同法11条1項の適用を受ける余地はなく、Xが支払を受ける預貯金利子等(以下「本件預貯金利子等」という。)については、その支払の際、所得税が源泉徴収される(同法212条3項)。また、Xは、法人税法2条6号の公益法人等に該当し(同法別表第2)、収益事業から生じた所得以外の所得については法人税が課されず(同法7条)、本件預貯金利子等に係る所得税については二重課税の問題は生じないから、同法68条1項の規定を適用する余地はなく、Xの法人税の額から本件預貯金利子等に係る所得税の額を控除することはできず、また、法人税の額から控除しきれなかった所得税の額の還付を求めることもできない(同条2項)。
以上によれば、本件事業年度の法人税額につき所得税の額を控除しなかったことに法律の解釈適用の誤りや計算過程の誤りは認められないから、本件更正の請求に理由がないとした本件通知処分は適法である。
② Xは、その目的や事業の公益性・公共性という点において公益法人と同等といえるXに対する本件通知処分は、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであって、違法であると主張する。しかしながら、上記のとおり、Xの法人税の額から本件預貯金利子等に係る所得税の額を控除することはできず、その点に裁量の余地はないから、Xの上記主張は失当である。
③ Xは、(イ)所得税法11条1項、別表第1の「公共法人等」に、公益法人と同様、非営利型法人をも掲げることにより、その支払を受ける利子及び配当等につき所得税を課さない公共法人等に非営利型法人を含め、あるいは、(ロ)法人税法68条を改正して、非営利型法人が支払を受ける利子及び配当等について源泉徴収された所得税の額を法人税の額から控除し、それでも控除しきれない部分についてはこれを還付する内容の改正をすべきであったのに、これと異なる不適切な法改正を行ったもので、このような本件立法行為は違憲、無効であり、それに基づく本件通知処分は違法である旨の主張をする。
しかしながら、仮に、Xの主張するような本件立法行為の違憲、無効が認められたとしても、そのことによって、直ちに、上記(イ)又は(ロ)のような規定が創設されたことになるものとみるべき法的根拠はない。
④ 源泉徴収された利子及び配当等に対する所得税については、法人税法68条、78条1項、74条1項3号による場合を除いて、これを利子及び配当等の受領者である内国法人に直接還付すべきことを定める法律上の規定は存在しない。したがって、上記のようなXの主張を前提としたとしても、本件預貯金利子等に対する所得税の額を法人税の額から控除し、それでも控除しきれない部分について還付を受けることができることになる法律上の根拠はないというべきであって、本件立法行為の違憲、無効を理由として本件通知処分が違法となる旨のXの主張は、その前提を欠くものといわざるを得ず、失当である。
⑤ 公益法人については、それ以外の一般社団・財団法人に比して、その高い公益性の保持が制度的に担保されているといえることからすれば、上記のような公益法人と非営利型法人との間の課税上の取扱いの区別は、その目的との関連で著しく不合理であることが明らかということはできない。また、非営利型法人が支払を受ける利子及び配当等について所得税を課することとする改正や、非営利型法人が支払を受ける利子及び配当等について源泉徴収された所得税の額を法人税の額から控除し、控除しきれなかった税額を還付するよう法人税法68条を改正しなかったことが、上記目的との関係で必要性又は合理性を欠くことが明らかということもできない。したがって、本件立法行為が憲法14条1項、29条に違反するものということはできない。