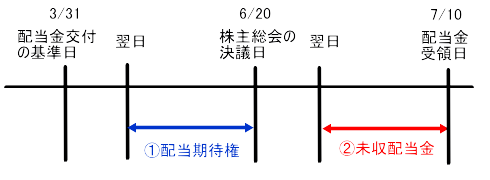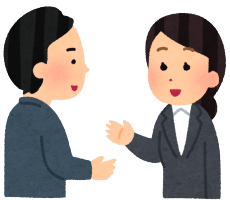
概要
例えば、夫が含み損のある株式A(取得価額150万円、市場時価100万円、相続税評価額100万円)を保有していたとします。この株式Aを、妻に贈与した場合、基礎控除110万円の範囲内なので、贈与税がかからずに妻は株式Aを取得できます。
そして、妻がすぐに株式Aを100万円で市場で売却した場合、取得価額は夫の取得価額を引き継ぐので、譲渡損はマイナス50万円となります(売却価額100万円-取得価額150万円)。
また、妻が自分が取得していた株式B(取得価額100万円)を、市場で150万円で売却した場合、譲渡益は50万円となります(売却価額150万円-取得価額100万円)。
株式A、株式B(共に上場株式とします)の譲渡が同じ年に行われれば、妻の株式譲渡損益は、結果、0円となります。同様なことが、親子間でも行えます。
問題は、このような贈与、株式譲渡による節税方法は、租税回避行為であるとして、税務署から否認されないのかということです。
同族会社とその株主等の取引については、同族会社の行為計算否認規定がありますが、その他の、例えば、上記のような個人間の取引のような場合に、一般的に租税回避行為を否認することができるとする規定はありませんし、学説、判例ともこれには否定的です。
ただし、課税庁は、過去の事例をみると、否認規定の有無に拘わらず否認を行ってきたことが幾度かあります。また、贈与、売却行為に不備等があれば、贈与、売却行為そのものが否認される可能性はあるといえます。
もっとも、上記のような少額なケースまで、否認してくることは考えにくいですが。
学説、判例
金子宏・租税法第24版139頁より引用
「法律の根拠がない限り租税回避行為の否認は認められないと解するのが、理論上も実務上も妥当であろう」
最高裁判所第二小法廷平成23年2月18日判決(判タ1345号115頁)の補足意見
「個別否認規定がないにもかかわらず、この租税回避スキームを否認することには、やはり大きな困難を覚えざるを得ない。けだし、憲法30条は、国民は法律の定めるところによってのみ納税の義務を負うと規定し、同法84条は、課税の要件は法律に定められなければならないことを規定する。納税は国民に義務を課するものであるところからして、この租税法律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず、これを規定する条文は厳格な解釈が要求されるのである。明確な根拠が認められないのに、安易に拡張解釈、類推解釈、権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って、租税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。」