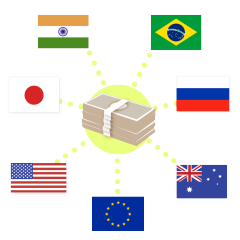保有する株式を売却すると同時に、同一銘柄の株式を購入することをクロス取引といいます。
法人の場合
法人がクロス取引をした場合は、売買目的有価証券を除いて、その売買取引はなかったものとして売買損益を認識しないこととされています(法基通2-1-23の4、平成12年に明確化)。
このような規制がなければ、例えば、保有し続けたい銘柄の株式であり、取得価額より時価が下がっている場合、いったん、売却して同時に取得すれば、実態として保有したままで売却損を計上(含み損を実現化)することができるということになります。つまり、決算時の損益をコントロールできてしまいます。
なお、期末時価評価を行う売買目的有価証券については、期末において、取得価額より時価が下がっている場合は評価損が計上され、法人税法上、損金の額に算入されます。
つまり、法人も、わざわざクロス取引をするメリットがなく、課税庁も規制する実益がないため、売買目的有価証券は対象とされていません。
クロス取引の規制対象になる売却と購入は、同日だけとは限らないと解されています(法基通2-1-23の4注1)。具体的に、売却と購入が何日離れていないと規制の対象になるか判断に迷いますが、金融商品会計に関するQ&A「Q12:いわゆるクロス取引が認められないのはなぜですか。 」では、以下のように記載されています。
例えば、金融資産を売却した直後(5営業日までは直後と考えられます。)に同一の金融資産を購入した場合又は金融資産を購入した直後に同一の金融資産を売却した場合であって、それらの取引における譲渡価格と購入価格がともに取引時の時価であるからといって必ずしも売却処理が認められるわけではなく、実質的に相対取引になっていると解される等、取引の実態によっては売却処理が否定されることもあります。
法人税は公正処理基準を前提(法法22④)としており、もともと、法人税法基本通達2-1-23の4は、金融商品の会計基準の導入に合わせて創設された経緯があります。
よって、法人税においても、最低でも5営業日(土日を挟んで1週間)を超えた日数でないと、危ないと思います。
法人税法基本通達2-1-23の4(売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引)
同一の有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券を除く。)が売却の直後に購入された場合において、その売却先から売却をした有価証券の買戻し又は再購入(証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託をしている場合の当該証券業者等からの購入又は当該証券業者等に購入の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託をしている場合の当該購入を含む。)をする同時の契約があるときは、当該売却をした有価証券のうち当該買戻し又は再購入をした部分は、その売却がなかったものとして取り扱う。
(注)1 同時の契約がない場合であっても、これらの契約があらかじめ予定されたものであり、かつ、売却価額と購入価額が同一となるよう売買価額が設定されているとき又はこれらの価額が売却の決済日と購入の決済日との間に係る金利調整のみを行った価額となるよう設定されているときは、同時の契約があるものとして取り扱う。
2 本文の適用を受ける取引に伴い支出する委託手数料その他の費用は、当該有価証券の取得価額に含めない。
3 購入の直後に売却が行われた場合の当該購入についても同様に取り扱う。
個人の場合
個人の場合は、市場取引などの場合はクロス取引による売却でも、株式の譲渡として認められ株式の譲渡損益が計上できます(個人が上場・店頭売買株式を売却するとともに直ちに再取得する場合の当該売却に係る源泉分離課税の適用について(法令解釈通達)平成12年3月17日課資3-2等)。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/joto-sanrin/000317/01.htm
ただし、同一特定口座内において、クロス取引を同一日に行う場合は譲渡損益の計算に注意をしてください。同一銘柄の株式を同一日内に複数回取得し、同じ日に売却した場合の取得価額の計算方法は、特定口座か、それ以外(一般口座等)で計算方法が違ってきます。
特定口座の場合、同一銘柄の株式を同一日内に複数回取得し、同じ日に売却した場合は、まず同日中の全ての取得があったものとして、その後に売却があったものとして計算します(措令25の10の2①三)。
下がりしている保有株式を売却すると同時に、同一銘柄の株式を同株数、同価額で購入する取引によって生じた売却損について、これを租税回避行為として否認することはできないとされた事例(平成2年4月19日裁決・裁事39集106頁)
値下がりしている保有株式を売却すると同時に、同一銘柄の株式を同株数、同価額で購入する取引によって生じた売却損について、原処分庁は、かかる取引は手数料等の実損を生じるだけ積極的な利益追求としてのメリットは全くない、株式売却損を発生させ、他の売買益と通算して税負担を減少させる目的で行ったものと認められるから、所得税法に内在する実質課税の条理に基づき、本件取引はなかったものとして雑所得の金額を計算すべきである旨主張する。
しかし、[1]本件売却損は、保有株式の値下がりによる損失を現実の売却により顕在化させただけであって、意図的に作り出したものではないから、結果として損失が生じたとしても、不自然、不合理なものとはいえないし、[2]保有株式の値下がりによる損失を顕在化させる目的で本件取引をしたものであっても、株式取引が極めて経済的危険の多い取引であり、所得税が経済取引上考慮されるべき経済的負担であることを考えると、そのような目的があるからといって、これを不自然、不合理として否定することはできず、[3]現実の取引によって値下がり損失を実現している以上、評価損と同視することはできず、仮装ないし不自然な取引とはいえないから、その行為は租税回避行為に当たらない。