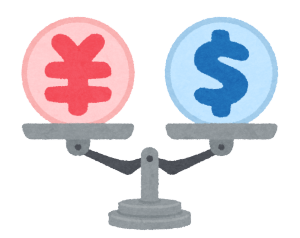
概要
相続した外貨預金を相続人が円転した場合、為替差損益をどう計算するのか判断に悩む納税者、税理士は多いでしょう。
このことについては、2つの説があります。
仮定として、被相続人が生前に米ドル1万ドルを100万円(1ドル=100円)で取得していたとします。被相続人が亡くなった日の為替レートは1ドル=130円だとします。そして、米ドルを相続した相続人が1ドル=150円の時に1万ドルを150万円に円転したとします。
①被相続人が1万ドルを100万円(1ドル=100円)で取得
②被相続人が亡くなった日の為替レートは1ドル=130円
③相続人が1万ドルを150万円(1ドル=150円)で円転
(1)被相続人が米ドルを取得した時の円換価額が相続人に引き継がれる
被相続人が米ドルを取得した時の円換価額が相続人に引き継がれるとした場合、相続人が1万ドルを150万円(1ドル=150円)で円転した時の雑所得の計算は以下となります。
150万円-100万円=50万円
(2)被相続人が米ドルを取得した時の円換価額は相続人に引き継がれない
(被相続人)被相続人が亡くなった日に精算をしたと考え、いったん、為替差損益の計算(所得税の準確定申告)をします。
130万円-100万円=30万円
(相続人)被相続人が亡くなった日の為替レートによる円換価額で相続人は取得をしたとなるので、相続人が円転した時の雑所得の計算は以下となります。
150万円-130万円=20万円
私見
上記に関するものを税務裁判例で探しましたが、見つかりませんでした。ですから、これから記載することは私見にすぎませんので注意をしてください。
私は、「(1)被相続人が米ドルを取得した時の円換価額が相続人に引き継がれる」と思います。 理由は、所得税法67条の4の条文を素直に読んで問題ないと考えられるからです。
| 所得税法67条の4 居住者が第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。 |
所得税法67条の4は、平成23年度税制改正により創設(平成23年分以後の所得税について適用)されましたが、平成23年度税制改正の解説(200~201頁)では、以下のように記載されています。
| 相続税・所得税の課税関係において(略)土地、株式等の値上がり益と定期預金の既経過利子等とは本質的に変わるところがないにもかかわらず、被相続人に生じている未実現の利得について実現段階で相続人に課税されることについて、前者には所得税法60条1項という明文の規定がおかれ、後者には明文の規定がないことが考慮され、現行のこの取扱いについて、確認的な意味で立法的手当てが講じられました。 具体的には、相続等により定期預金、株式等その他の金融資産を取得した場合において、その相続等に係る被相続人等に生じている未実現の利子、配当その他の所得は、実現段階で相続人等に課税される旨が規定されました。 すなわち、居住者が次の①又は②の事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合におけるその資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続きその資産を所有していたものとみなして、所得税法の規定を適用することとされました(所法67の4)。 ① 贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。) ② 個人に対する時価の2分の1未満の価額の対価での譲渡 |
未実現の利子、配当その他の所得と記載されていますが、為替差損益そのものは記載されていないので、「その他の所得」に為替差損益が含まれているのか悩みます。
また、大阪地裁令和3年11月26日判決(税資271号順号13635)「所得税法67条の4の趣旨」に関する判示(下記記載)においても、利子、配当所得の繰り延べについて主に述べており、為替差損益の繰り延べそのものについて述べられていません。
ただし、譲渡所得課税に対する繰り延べ規定(所法60①)と同じ性質の課税である旨を法令上明らかにするため所得税法67条の4が創設されたと考えれば、利子、配当所得の繰り延べ(未実現)だけでなく、為替差損益の繰り延べ(未実現)も含まれると考えられます。
つまり、山林又は譲渡所得の基因となる資産の相続等による移転に関するものは規定(所法59,60)されていたが、それら以外の資産の相続等による移転に関するものが規定されていなかったので所得税法67条の4が創設されたと素直に考えてよいのではないかと思います。
もっとも、実際に申告する場合は、事前に所轄の税務署に相談に行かれることをお勧めいたします。
なお、納税者の数名の方がそれぞれの所轄の税務署にこの点についてどのように考えるのか相談に行きましたが、全員、「(1)被相続人が米ドルを取得した時の円換価額が相続人に引き継がれる」という回答でした(もっとも数名にすぎませんが)。
別段の定め
所得税法67条の4は「別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。」と規定されています。
つまり、「別段の定め」がある場合は、引き続き当該資産を所有していたものとみなさないということになります。
「別段の定め」とは、棚卸資産の贈与、暗号資産の贈与等があった場合にはその贈与等の時における価額により雑所得の総収入金額に算入する規定(所法40①、所令119の6②)等が該当します。
外貨預金を取得した時の円換価額が不明の場合
被相続人が外貨預金を所有していて亡くなった場合、被相続人が外貨預金を取得した時の円換価額を相続人が把握できないこともあるでしょう。
為替差損益と同じ雑所得に該当する暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められています(所基通48の2-4)が、為替差損益は概算取得費の適用はありません。もっとも、円とドルの関係でいえば、円転価額の5%相当額を取得時の円換算額とするのはばかげた話だと思います。
ですから、相続した外貨預金の円換算額が不明の場合、理論値で納税者にとって一番不利なレートを利用して申告すれば、税務署も否認はしてこないと考えられています。
例えば、いつからいつまでに取得したという事がわかれば、その間の納税者にとって一番不利なレートで取得したとすればよいでしょう。
なお、いつ取得したかもわからない場合は、過去の納税者にとって一番不利なレートで取得したとすればよいでしょう。例えば、円とドルの関係でいえば、過去最大の円高としては2011年10月31日の1ドル=75円32銭となります。
ただし、このようなことがないように、親は亡くなる前に、相続した子供が困らないように所有している外貨預金の円換算額をメモ書きして残すべきでしょう。
大阪地裁令和3年11月26日判決(税資271号-133順号13635)「所得税法67条の4の趣旨」に関する判示
ア 所得税法67条の4は、最高裁平成22年判決についての検討を踏まえ、平成23年法律第82号による所得税法の改正により新設された規定である。同条は、最高裁平成22年判決の考え方からすれば、定期預金の既経過利子や株式の配当期待権に対する課税についても、違法な二重課税が生じているのではないかという疑義を生じかねないことから、所得税法60条1項による課税の繰延べと同じ性質の課税である旨を法令上明らかにすることで、上記の解釈上の疑義を立法的に解決したものと解される。その理由は以下のとおりである。
イ ここで、所得税法60条1項1号による課税の繰延べの趣旨につき検討する。
そもそも譲渡所得とは、資産の譲渡による所得であり(所得税法33条1項)、このような譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりにより所有者に帰属する増加益を所得として、資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税するという点に趣旨がある。
資産の相続があった場合、それが限定承認などの一定の事由によるときは、その時点での価額に相当する金額により譲渡があったものとみなされて当該譲渡所得に課税されるが(所得税法59条1項1号)、それ以外の場合には、譲渡所得の金額の計算に当たっては、当該相続人が引き続き所有していたものとみなされる(所得税法60条1条1号)。譲渡所得課税の趣旨に鑑みれば、相続により相続人が資産を取得した場合であっても時価により譲渡があったものとみなして課税の対象とするのが素直であるが(所得税法59条1項1号参照)、相続の場合は相続時点で資産の増加益が具体的に顕在化せず、その時点で課税することに納税者の納得を得難いため、課税を留保し、当該相続人が資産を譲渡して増加益が顕在化したときに清算して課税することとした。これが、課税の繰延べを定めた所得税法60条1項1号の趣旨である(最高裁平成17年2月1日第三小法廷判決・裁判集民事216号279頁参照)。換言すれば、被相続人による当該資産(典型的には値上がり中の土地)の取得時から相続時までの間に被相続人の下で潜在的には発生していた増加益(被相続人の取得時から相続時までの増加益)に対する譲渡所得課税は、相続時に被相続人に対するものとして行うのではなく、譲渡時に相続人に対するものとして、相続時から資産譲渡時までの間に相続人の下で具体的に顕在化した増加益(相続時から相続人の譲渡時までの増加益)に対する譲渡所得課税に併せて行うこととして、繰延べをしているのである。やや比喩的にいえば、資産の相続があった場合の譲渡所得課税(所得税法60条1項1号)は、「被相続人の取得時から相続時までの増加益」に対する(被相続人の下で潜在的に存在した)譲渡所得課税と「相続時から相続人の譲渡時までの増加益」に対する(相続人の下で具体的に顕在化した)譲渡所得課税を併せる形で、「被相続人の取得時から相続人の譲渡時までの増加益」に対する譲渡所得課税として相続人に対して実行されている。
ウ 他方、相続人が被相続人から資産を相続した場合、相続税は、原則として当該資産を時価で評価した上で当該時価を標準として課税される(相続税法22条)。
当該資産の時価は、被相続人の取得価額に取得時から相続時までの増加益を加算したもの(「被相続人の取得価額」+「被相続人の取得時から相続時までの増加益」)ということができるから、これに相続税が課税されることとなる。
エ 以上を前提とすると、被相続人から資産を相続した相続人にとって、当該資産の時価のうち、被相続人の取得時から相続時までの増加益に相当する部分は、上記のとおり相続税の対象となっている上に、上記のとおり所得税(譲渡所得課税)の対象ともなっているものとして、同一の経済的価値に対する相続税と所得税との二重課税とみられかねないとはいえる。
しかしながら、相続した資産に係る被相続人の取得時から相続時までの増加益に対する譲渡所得課税は、被相続人の下で潜在的に存在した増加益に対する課税、すなわち本来的には被相続人固有の所得に対する譲渡所得課税を相続人に繰り延べたものである。当該所得の本来的な帰属主体が異なる以上、これをもって、同一の経済的価値に対する相続税と所得税との違法な二重課税と評価することはできない。
オ これと同様のことは、被相続人の預金債権を相続人が相続した場合、被相続人の株式を相続人が相続した場合にも妥当する。
すなわち、課税実務において、従前より、相続人が満期前の定期預金を被相続人から相続した場合、当該相続人に対しては、相続税が、当該定期預金を「定期預金元本+既経過利子-既経過利子に係る源泉所得税相当額」の計算式で評価した(評価通達203参照)上で課される一方、所得税が、定期預金の利子(預入から満期までの利子)の全額につき課されて(満期日にまとめて相続人から源泉徴収されて)きた。また、相続人が株式の配当金交付の基準日(当該配当に係る基準日)の後で配当金交付の効力が発生する日(当該配当に係る株主総会決議等の日)の前に被相続人から株式を相続した場合、当該相続人に対しては、相続税が、当該株式の配当期待権を「課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額-当該金額に係る源泉所得税相当額」の計算式で評価した〔評価通達168(7)、193参照〕上で課される一方、所得税が、配当支払日に実際に受け取る配当の全額につき課されて(相続人から源泉徴収されて)きた。
このような課税実務は、いずれも相続された資産について被相続人の下で潜在的に存在した被相続人固有の所得に対する所得課税を相続人に繰り延べているだけであるという考え方を前提とするものと解される。このような考え方からすれば、当該所得の本来的な帰属主体が異なる以上、これをもって、同一の経済的価値に対する相続税と所得税との違法な二重課税と評価することはできない。
しかし、当該預金債権又は当該株式を相続した相続人からみた場合、これらの課税実務が、最高裁平成22年判決の趣旨に抵触し、定期預金の既経過利子や株式の配当期待権について、同一の経済的価値に対して違法な二重課税が生じているのではないかとの疑義が生じかねないものであった。
そこで、上記説示のとおり、所得税法67条の4は、これらの課税実務が所得税法60条1項1号による課税の繰延べと同じ性質の課税であることを法令上明らかにすることで、上記解釈上の疑義を立法的に解決したものと解するのが相当である。

