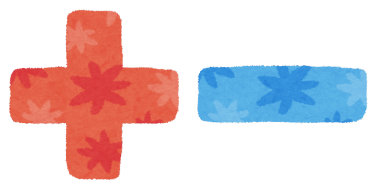概要
法人の段階で納付した法人税に相当する金額は、その配当等を受けた個人が納付する所得税額から控除(配当控除)するという仕組みとなっています(所法92)。
このため、内国法人とその株主である個人との中間段階に、他の法人が株主として存在するときは、その中間段階にある法人が受け取る配当等の額にそのまま課税すると、最終的に個人段階で納付する所得税額から法人税相当額を控除する際に、中間段階で法人税が課税された回数に応じて、その都度、配当控除額を定めなければなりません。
しかし、そのような計算は技術的に不可能であるため、株主である法人が受け取った配当等の額については、益金の額に算入しないこととしてこの問題を解決しています。
法人が他の内国法人から配当等を受けた場合には、その受取配当等は、企業会計上では収益として計上します。一方、法人税法上は一定の申告手続を条件に、その配当等に係る株式等の区分に応じて、その配当等の額の全額又は一定の算式により計算した金額を益金の額に算入しないこととしています(法法23)。
なお、法人企業の投資目的での株式保有の高まり等の諸情勢も考慮し、持株比率が低い株式等に係る配当等の額については、二重課税を完全には調整せず、益金の額に算入することとしています。
益金不算入の対象となる受取配当等
受取配当等の益金不算入の規定は、法人・個人間の二重課税を避ける趣旨のものであり、その適用を受ける剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配は、株式等又は出資に係るものに限られます。
したがって、同じ配当という用語が使われていても、次のとおり益金不算入となるものとならないものとがあります。
(1)益金不算入となるもの
① 剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額(法法23①一) 期末配当、中間配当
② 投資信託及び投資法人に関する法律137条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配を除く。)の額(法法23①二、法規8の4)
③ 資産の流動化に関する法律115条1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額(法法23①三)
④ 特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配額(措法67の6)
⑤みなし配当(法法24)
⑥名義株等の配当(法基通3-1-1)
(2)益金不算入とならないもの
① 外国法人、公益法人等又は人格のない社団等から受ける配当等の額(法法23①)
② 保険会社の契約者配当の額(法法60①)
③ 協同組合等の事業分量配当等の額(法法60の2)
④ 証券投資信託の収益の分配の額(旧法法23①三、旧法令19)
⑤ 特定目的会社及び投資法人から受ける配当等の額(措法67の14④、67の15④)
⑥名義書換え失念株の配当(法基通3-1-2)
⑦信用取引に係る配当落調整額(法基通3-1-6)
受取配当等の益金不算入額の計算
法人の保有する株式等を、①完全子法人株式等(株式等保有割合が100%のもの)のグループ、②関連法人株式等(株式等保有割合が1/3を超えるもの)のグループ、③その他の株式等(株式等保有割合が5%超1/3以下のもの)のグループ及び④非支配目的株式等(株式等保有割合が5%以下のもの)のグループの四つに分けて、それぞれ次の①から④までに掲げる算式により計算した額の合計額が受取配当等の益金不算入額となります(法法23①④⑤⑥)。
① 完全子法人株式等に係る配当等の額 (全額)
② 関連法人株式等に係る配当等の額 ─ 関連法人株式等に係る負債利子額
③ その他の株式等に係る配当等の額 × 50%
④ 非支配目的株式等に係る配当等の額 × 20%
| 区 分 | 株式等保有割合 | 益金不算入の割合 | 負債利子の控除 |
|---|---|---|---|
| ①完全子法人株式等 | 100% | 100% | なし |
| ②関連法人株式等 | 1/3超~100%未満 | 100% | あり |
| ③その他の株式等 | 5%超~1/3以下 | 50% | なし |
| ④非支配目的株式等 | 5%以下 | 20% | なし |
①完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等をいいます。
②関連法人株式等とは、内国法人(完全支配関係がある他の法人を含む。)が他の内国法人の発行済株式等(自己株式等を除く。)の3 分の1 超を、その配当等の前に最後にされた配当等の基準日等の翌日(その配当等の基準日等から起算して6月前の日以前の日である場合には、その6月前の日の翌日)からその配当等の額に係る基準日等まで引き続き有している場合における当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く。)をいいます。
③その他の株式等とは、完全子法人株式等、関連法人株式等、非支配目的株式等のいずれにも該当しない内国法人の株式等をいいます。
④非支配目的株式等とは、内国法人(完全支配関係がある他の法人を含む。)が他の内国法人の発行済株式等(自己株式等を除く。)の5 %以下を、配当等の額に係る基準日等に有する場合における当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く。)をいいます。
なお、短期保有株式等に係る配当等(法法23②)については、益金不算入が認められません。完全子法人株式等は、計算期間を通じて100%保有されているものをいうため、短期保有株式等に該当することはありません。
また、短期保有株式等がある場合には、その短期保有株式等を有していないものとして非支配目的株式等であるかの判定を行います(法令22の3②)。
受取配当等の益金不算入制度の適用を受けるための手続き
受取配当等の益金不算入の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、その記載された金額を限度として適用されます(法法23⑦)。